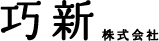龍田の蔵
ブログ
3ヶ月間の月日を掛けて、蔵の改修工事をお世話になりました。

こちらの御施主様は、これまで様々な工事を受注して頂きました。
最後の工事は、御施主様の念願であった 蔵を施工させて頂きました。


バス板下地にモルタルラミテクト・異形ラスを貼り軽量モルタルで下塗り。
乾燥後に上裏・壁面は、自社製造した砂漆喰中塗りし、10mm目のグラスファイバーネットで全面ネット補強。
鉄格子も特注で新調しました。



笠木は、4分目地棒を割り付け、菊水山砂・菊池川砂利を骨材にモルタル搔き落とし。
腰壁は、5分目地棒を割り付け、菊水山砂・カーボンブラックで墨モルタルドイツ壁。
巾木は、カナリア石・錆御影石・顔料で人造洗い出し。

仕様・デザインはお任せでしたので、私の好きな擬石モルタルで建物に「重厚」を求めました。
又、意匠を求めた誘発目地は、笠木4分、腰5分と使い分け、黒モルタルと白モルタルで覆輪目地仕上げ。
覆輪目地と言えば代表的な建物は、東京駅丸の内駅舎。
約100年前に西洋建築で使用されてある赤レンガの美しさを際立たせる為に生まれた、日本独自の技法であります。
目地の断面が半円形で中央部を「かまぼこ」のように盛り上げる事により目地を強調しつつ、「柔らかい」印象が見受けられると言われています。


覆輪目地を触れた事で、先人達の知恵や感性を改めて感じる事が出来ました。
又、明り取りの窓廻りは、漆喰蛇腹引きで意匠付け。



仕上工程は、悪天候で思うように行きませんでしたが、社員に支えられ、如何にか納める事が出来ました。





中塗りの砂漆喰、仕上の油漆喰は、適度な強度、施工性、色味、漆喰壁としての私が考える理想の「在り方」を求めて、石灰の種類、スサの分布、海苔の濃度を検証し、バランスを考え配合しています。
モルタルや洗い出しも骨材の大きさを変えて粒度分布を求め、経年変化を「風化」として味わい深く想像する。
素材の特性を考え配合を調整し、機能性や耐久性を変化させ、様々な手法で演出できることは、左官の醍醐味かもしれません。
今後も頂いたご縁を大切にし、感謝を忘れずに「より良きもの」を目指して取り組んで行きたいと思います。