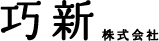京都研修1
ブログ
6月6~8日で京都へ研修に行って来ました。

京都へ行ったの目的として、聚楽会が開催している 京壁 向上訓練 に参加するためです。
毎年1,2回は京都へ行ってますが、向上訓練に合わせて建築を学ぶ旅にもしています。
今回は、京都御所と桂離宮へ行きました。





京都御所は、明治維新まで天皇の住まいであり、桓武天皇が奈良の平城京より長岡京(京都府)を経て、延暦13年(794)に平安京に都を移されたのが始まりです。
平安京は、南北約5.2km、東西約4.5kmの方形で、中央の朱雀大路(現在の千本通り)により左京と右京に分けられ、大小の道で碁盤の目の様に区画されていました。
元弘元年(1331)に光厳天皇がここで即位されて以降、明治2年(1869)に明治天皇が東京に移られるまでの約500年間、天皇のお住まいとして使用されました。
この間も幾度もなく火災に遭い、その都度再建が行われ、当初は現在の敷地の半分以下であったが、豊臣秀吉や徳川幕府による造営により敷地は次第に拡大され、現在の京都御所であります。
京都御所は築地塀に囲まれた南北約450m、東西約250mの方形で、面積は約11万m2。
敷地内では、古代以来の日本宮殿建築の歴史と文化が見られると同時に、回遊式庭園の御池庭、献上の石や灯篭を配した御内庭など、木々や花など季節の変化も楽しめるものとなっています。


趣ある石灯篭と植物。
歴史を感じ、手で刻まれたであろう灯篭の存在力。
灯篭好きの私には、何とも言えない名作でした。
御所内を見学して、お昼御飯は楽しみにしていた京都ラーメンを食べました。
京都ラーメンと言えば第一旭。
しっかり堪能出来ました。


京都駅に戻り、市営バスに乗って、桂離宮のある桂坂へ。
入場は予約制なので、時間を調整して向かいました。





国有財産である桂離宮。
桂離宮の歴史は、後陽成天皇の弟・八条宮初代敏仁親王により、宮家の別荘として創建されたものであります。
寛文2年(1662年)頃までに在来の建物や庭園に巧みに調和させた中書院、新御殿、月波楼、賞花亭、笑意軒等を新増築されました。
池や庭園にも手を加え、ほぼ今日に見えるような山荘の姿に整えられました。
特に桂棚及び付書院で知られている新御殿や御幸道などは、八条宮家その後常磐井宮、京極宮、桂宮と改称されて明治に至り、明治14年(1881年)12代淑子内王がなくられるとともに絶えた。宮家の別荘として維持されたきた桂山荘は、明治16年(1883年)宮内省所管となり、桂離宮と称されることとなるが、創建以来永きにわたり火災に遭うこともなく、ほとんど完全に創建当時の姿を今日に伝えています。
庭園、建築共に遠州好みの技法が随所に認められることから、桂離宮は遠州の影響を受けた工匠、造園師らの技と敏仁親王及び智忠親王の趣味趣向が高い次元で一致して結実した成果であり、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、修学院離宮と共に皇室用財産として宮内庁が管理されてあります。





左官屋目線で拝見すると、壁に使用されてある土は稲荷山黄土。
仕上は、水鏝撫で仕上。
左官技法の最高仕上。
時代とともに風化しつつも、上品な肌に、作者の作為を感じます。
御幸道のあられこぼし、書院群の杮葺きむくり屋根、回遊式庭園、どれもが圧巻の一言でした。
有意義な一時を過ごし、宿のある堀川五条へ戻り、夕飯を取りながら一人旅の夜は更けていきました。

次回へ続く。